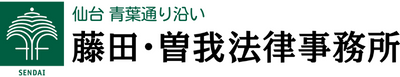刑事事件:保釈のアピールポイントが明確になりました

刑事訴訟法が改正されました
今年(2016年)の5月24日,刑事訴訟法等の一部を改正する法律が成立しました。
改正法の目玉は,取調べの可視化です。
村木元厚生労働省局長事件のように,密室での取調べによる冤罪事件が問題となったため,裁判員裁判事件など一部の事件にとどまりますが,取調べの全過程の録音・録画が捜査機関に義務付けられることになりました。
取調べの可視化はまだ施行されていませんが(平成31年6月までに施行),改正法には他にもいくつか改正点があり,既に施行されているものもあります。
必要的保釈と裁量保釈
既に施行されている改正点の一つに,「裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化」があります(平成28年6月23日施行)。
保釈の請求があったとき,裁判所は,「被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき」などの6つの除外事由のいずれにも当たらない場合,保釈を許可しなければなりません。
これを必要的保釈といいます。
他方,必要的保釈に該当しない場合でも,裁判所は裁量で保釈を許可することができます。
これを裁量保釈といいます。
裁量保釈の考慮事情
これまで,刑事訴訟法は,裁量保釈について「裁判所は,適当と認めるときは,職権で保釈を許すことができる。」としか定めていませんでした。
改正法では,「裁判所は,保釈された場合に被告人が逃亡又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか,身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上,経済上,社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し,適当と認めるときは,職権で保釈を許すことができる。」と改正されました。
予測可能性からアピールポイントに
裁判所の裁量といっても,サイコロやくじ引きで決めてはいけないことは当然です。
しかし,旧法の「裁判所は,適当と認めるとき」だけでは,どのような事情があれば認められるのかが今一つ,分かりませんでした。
しかし,改正法によれば,裁判所が考慮すべき事情は以下のとおりに整理されます。
- 保釈された場合に被告人が逃亡し,または罪証を隠滅するおそれの程度
- 身体の拘束の継続により被告人が受ける不利益
- その1 健康上の不利益
- その2 経済上の不利益
- その3 社会生活上の不利益
- その4 防御の準備上の不利益
- その他の事情
したがって,ある事件で裁量保釈が認められそうか否かは,これらの事情をもとに予測することができます。
裏を返せば,裁量保釈を受けるためには,これらの事情に沿った主張を行うことが必要です。
私も,保釈請求をする際は,これらの事情をアピールポイントとして意識したいと思います。
この記事を書いた弁護士

-
弁護士 曽我陽一(新潟の米農家出身。趣味はマラソン)
1998年 東北大学法学部卒
2001年 弁護士登録(東京弁護士会)
2008年 宮城県仙台市青葉区に曽我法律事務所を開設
2022年 藤田・曽我法律事務所開設
2022年4月~ 東北大学大学院法学研究科教授
お客様にとって「話しやすさ」を重視しています。法律問題でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
最新の投稿
- 2021年4月9日弁護士コラムあきらめるな経営者!事業再生・再建セミナー
- 2020年12月28日弁護士コラム仙台光のページェント
- 2019年7月11日カテゴリー>企業法務取引先が倒産した場合の法的対応・事前対策:仙台商工会議所月報「飛翔」2019年7月号に寄稿しました
- 2018年10月10日カテゴリー>企業法務仙台商工会議所月報「飛翔」に寄稿しました:企業間の契約締結の注意点